<う蝕の分類と治療法、詰め物・被せ物の種類について>
健口かわさきコラム NO.1
う蝕とは虫歯のことで歯が黒くなったり穴が開いたりして、冷たいものや温かいものでしみたり噛むと痛い、時には何もしていなくてもズキズキうずくようになることもあります。
虫歯の一番の原因は「ミュータンス菌」という細菌で口の中の糖分をもとに活発に活動し、酸を発生させ歯のエナメル質を溶かしてカルシウムやリンといった歯を構成する物質を流失させます。
以下に、う蝕の進行や治療法・治療の際に使用する際材料等の特性について解説します。
- Co
初期虫歯と言われる状態です。歯の表層のエナメル質が少し溶けた状態で茶色になったり白くなることもあります。歯の溝が黒くなったり、点で黒くなることもあります。
自覚症状はなく基本的には削ることはしません。再石灰化を促すためフッ素を塗布して様子をみることもあります。

- C1
エナメル質が溶けて穴があいた状態です。痛みはなく虫歯を削ってレジンという樹脂(プラスチック)を詰める治療を行います。

- C2
虫歯がエナメル質の下の象牙質まで進行した状態です。冷たいものでしみたり、神経の近くまで進行すると何もしていなくても痛みが出ることもあります。虫歯を削って詰め物を行います。(種類は以下に記載)痛みの状況によっては神経を取る(根管治療)こともあります。

*詰め物の種類
<保険診療の場合>
・コンポジットレジン:樹脂(プラスチック)を直接詰める方法。小さい範囲であれば1回で治療が終わるというメリットがある一方で広範囲になると形をうまく作りきれなかったり、詰めたレジンが欠けてくることもあります。
・メタルインレー:いわゆる銀歯。型を取って作製したものを接着剤で装着する方法。
強度は担保されますが、銀歯は徐々に腐食し溶解するため気が付かないうちに二次虫歯になっていることもあります。
・CAD/CAMインレー:レジン(プラスチック)にセラミック(陶材)を少し混ぜた素材を使用します。ハイブリッドレジンとも呼ばれる材料です。保険の範囲内で白くできるメリットがある一方で強度が高くなく破折リスクが高いです。着色や汚れも付きやすく見た目の劣化や虫歯・歯周病の原因となるプラークが付着しやすくなるため注意が必要です。
CAD/CAMインレーは歯の種類や残存歯数によっては適応にならないこともあるので事前に歯科医師に相談が必要です。
<自由診療の場合>
・セラミックインレー(e-max、オールセラミックス):強度や透明感が高くプラークも付着しにくいです。後述のジルコニアと比較してより見た目が自然で綺麗です。
・ジルコニアインレー:オールセラミックスと比較した際により強度が高いことが特徴です。
・金歯:見た目は目立ちますが銀歯のように腐食することは基本的になく虫歯にはなりにくいです。セラミックと比較して壊れるリスクも低いです。
- C3
虫歯が象牙質を超えて神経まで到達している状況です。冷たいものや、温かいものにしみたり、ズキズキうずくようになることもあります。(歯髄炎)根管治療によって根の中の治療を行い、クラウンという被せ物を装着します。(根管治療を行った歯は歯としての強度が脆くなるので被せ物をすることによって歯冠が破折することを予防します。)

*被せ物の種類
<保険診療の場合>
・メタルクラウン:銀歯
・CAD/CAMクラウン
各々、素材の特徴はインレーと同様
・硬質レジン前装金属冠:基本的に前歯に使用。銀歯の表面に硬質レジンという白い材料を張り付ける方法です。CAD/CAMと比較して見た目の透明感は落ちるもののクラウン自体が完全に破折するリスクは低いです。(表面に張り付けた硬質レジンが欠けたり剥がれてしまうことはあります。)
<自由診療の場合>
・セラミッククラウン(e-max、ジルコニア)
・金歯
インレーと同様の特徴です。
・陶材焼付金属冠(メタルボンド):陶材焼付用の金属の上に陶材を築盛するクラウンです。長い間使用されてきた実績があり、表面の陶材が欠けたりしても審美面で問題にならなければ必ずしもやり直しにはならず噛む力が強い人や歯ぎしり、食いしばりがある方でも使用しやすいです。
・ジルコニアセラミッククラウン:ジルコニアの裏打ちの上にセラミックを築盛する方法です。前歯に使用することが多く、金属を使わずに周囲の天然歯と調和させることができる被せ物です。
- C4
虫歯が歯冠を崩壊させるほどに進行し、根まで虫歯が及ぶ場合もある状況です。治療法として通常は抜歯を行い、入れ歯やブリッジ、インプラント(人工歯根)を選択することになります。
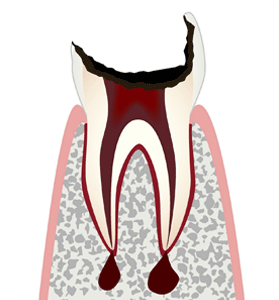
以上がう蝕についての進行程度による分類と治療法、治療に用いる材料についての特徴となります。
虫歯になってしまった場合、その進行程度によって治療回数や治療期間、費用も変わってきます。まずは歯の健康を維持するために日頃からご自宅での歯磨きに注力すること、歯科医院での定期検診の受診とプロフェッショナルなケアを受けることで予防を意識していくようにしましょう。
そしてもし虫歯になってしまった場合にはかかりつけ医とよく相談しながら治療を行うようにしましょう。
公益社団法人 川崎市歯科医師会 学術部
書いたひと 
医療法人社団陽優会 溝の口おくだ歯科クリニック
奥田 文俊 先生